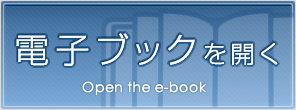「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 125/276
このページは 「人道研究ジャーナル」Vol.2 の電子ブックに掲載されている125ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
「人道研究ジャーナル」Vol.2
The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013明し、承諾が得られたら、調査者より母親に自己紹介と調査内容の説明を再度行い、了解が得られた後に参与観察及び聞き取り調査を行った。この場合、調査が強制にならないように母親に説明し、女性の意思を尊重することを遵守した。用語の定義1. PHC(Primary Health Center)とは、ナイジェリアでは公的ヘルスセンターであり、助産師、看護師、保健師らが常駐し、分娩介助、妊婦健診、産後健診、予防注射、家族計画や第一次医療を提供する外来などを実施している。ラゴスでは医師は、地区に1名メディカルオフィサーとして配置され、数か所のPHCを管理する。なお、PHCによっては24時間の患者の受け入れ体制をとっている施設と、昼間のみ外来を実施している施設に大別される。2.本研究でいう産褥管理とは、分娩第4期以降から、退院までの24時間と、それ以降、再び産後の健診を受けるためにPHCを訪れるまでの期間とした。結果1.調査対象者の背景1)助産師聞き取り調査を行った助産師15人の平均年齢は41.4±8.1歳であり、全員が看護師と助産師の有資格者であった。助産師としての平均勤務経験は15.4±7.1年、PHCでの平均勤務経験は4.9±6.6年であった。今回インタビューを行った助産師は病院などでの勤務経験を経てPHCで勤務をしていることが分かった。最終学歴は看護学校卒11人(71.4%)、看護大学卒1人(6.7%)、不明3人(20.0%)であった。2)産後健診を受けた母親(1)参与観察産後健診の参与観察を受けた母親は、調査表の通り14名であり、平均年齢は25.9±4.1歳であった。初産婦6人(42.9%)、経産婦8人(57.1%)で二人目3人、3人目2人、4人目3人であり、経腟分娩13人、帝王切開術による出産1人であった。出産場所はPHC5人(35.7%)、個人病院5人(35.7%)、TBA3人(21.4%)、公的病院1人(7.1%)であった。上記の結果、出産場所と産後健診を受ける施設の異なる人が多いことが分かった。(2)聞き取り調査産後健診後に産後の手伝いの有無について聞き取り調査をした母親は25人であり、平均年齢は28.1±4.5歳であった。初産婦8人(32.0%)、経産婦17人(68.0%)で二人目8人、3人目4人、4人目4人、5人目が1人であった。出産場所はPHC11人(44.0%)、個人病院5人(20.0%)、TBA5人(20.0%)、公的病院3人(12.0%)、家庭分娩1人(4.0%)であった。2.聞き取り調査による産後管理の方法についてPHCに勤務する助産師15名を対象に、出産2時間後から退院までの間に提供される産後管理の方法について聞き取り調査を行った。その結果、出産後、母親は産後用のベッドで休ませ、新生児もその横で一緒に寝かせる。そうすることで、母児を一緒に観察しながら、母親が新生児の育児になれるように支援する。また、新生児が啼泣すると、その都度母親に対しては授乳をするように促し、うまく授乳ができない場合は、授乳指導を行うという。母体の回復については、出産後2時間目に血圧測定を行い、出血状態と子宮の収縮や悪露の状態を観察した後、異常がない場合は退院まで継続して様子観察をする。一方、新生児の体外生活への適応に関する観察は、授乳状態の観察が中心であり、それ以外に、バイタルサインの測定などは実施しない。そして、出生直後の当日がPHCで予防接種を投与する日であれば、新生児にポリオワクチンを投与するという。退院日が予防接種日でない場合は、該当する日に来院するように説明するという。その後、出産後24時間以内に、なにも異常がなければ退院が決定し、母児共に帰宅させる。その際、産後6週間目に新生児の予防注射があるので、産後健診を受けるように説明する。また、HIV陽性の母親には、投薬方法と継続的な診察の必要性等を説明し、帰宅時には、家族が着替えなどを持参して徒歩または公共の乗り物を利用して帰宅させるという。以上が、助産師を対象に聞き取った産後管理の方法である。3.産後健診の時期と診察内容1)参与観察(表を参照)産後健診場面の参与観察は産後7週目2人、6週目7人、4週目1人、3週目1人、2週目3人、の14場面で行うことができた。なかでも6週目が最も多かった。これは、産後6週目にポリオ及び5種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、肝炎、インフルエンザ)人道研究ジャーナルVol. 2, 2013123