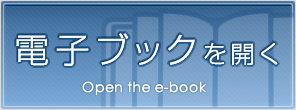「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 157/276
このページは 「人道研究ジャーナル」Vol.2 の電子ブックに掲載されている157ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
「人道研究ジャーナル」Vol.2
The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013については今もなお「トップ・シークレット」として公開されてはいない(Cf., Vincent VOLET,≪Sous les bombesa Tokyo. Les cables secrets de l’ambassadeur suisses. Document≫, Le Nouveau Quotidien, Lausanne, Mercredi 22 septembre1993, p.9)。(3)おそらくは≪j’allais oublier≫は挿入句であり、≪avec la croix-rouge japonaise≫という句は前述の≪la liaison a etablir≫に接続するのではないかと解釈する。文法的にみて不正確な文章になっているのは、筆者であるジュノー博士が考えながらタイプをしているためではないか。(4)当時、フリッツ・ビルフィンガー氏は中国地方に点在する連合国軍俘虜収容所の査察に派遣されていた(Cf., FritzBilfinger,“Diary to the report ? Report on the Evacuation of POW & CI in the Hiroshima sector”, september 17, 1945, BG3/51,Archives of the ICRC.三神国隆著『海軍病院船はなぜ沈められたか第二永川丸の航跡』、芙蓉書房、2001年刊、pp.227,254,262。枡居孝著『太平洋戦争中の国際人道活動の記録(改定版)』、日本赤十字社、1994年、p.30,210-211。)。(5)サムス大佐の回想録では「12トン」となっている(C・F・サムス著竹前栄治訳『DDT革命占領期の医療福祉政策を回想する』、岩波書店、1987年刊、pp.30-33)。二至村菁(にしむらせい)女史の著書でも「12トン」となっている(二至村菁著『日本人の生命を守った男GHQサムス准将の闘い』、講談社、2002年刊、p.184)。なお、ビルフィンガー氏が離日にあたってジュノー博士に提出した機密報告書「広島における原子爆弾の影響に関する報告書」(Report on the effects of the Atomic Bomb at Hiroshima)に添付されている添付第4書類、すなわち、連合国軍最高司令部から日本帝国政府あての英文覚書(Memorandum for: The Japanese Imperial Government. Through : CentralLiaison Office, No.1. From : The Supreme Commander for the Allied Powers.)の中では、「当該(広島)地域における日本人負傷者の救援の用に充てるために、約12トンの医薬品が赤十字国際委員会代表ビルフィンガー氏にあてて目下搬出中である」(Cf., Appendix 4 to Fritz Bilfinger’s confidential“Report on the Effects of the Atomic Bomb at Hiroshima”,Archives of the ICRC, A CL 16.06.02)と記されている。これは、サムス著前掲書に引用訳出されている資料と同一物であろう。では、どの時点で「15トン」となったのかが疑問である。医薬品が空輸された岩国海軍航空隊(日本海軍第五航空艦隊指揮下)の当直日誌が防衛研修所戦史室に保存されていれば、到着時点での総トン数を確認する必要がある。(6)本橋均陸軍軍医少佐、都築正男東京帝国大学医学部教授(外科学)。(7)中国軍管区司令部。(8)冨野康治郎氏のことである。冨野氏は、赤十字国際委員会駐日代表部の通訳として、広島へ医薬品を届け、なおも宮島で事務処理にあたっていたところ、1945年9月の枕崎台風に遭遇し、落命した(大佐古一郎「ドクター・ジュノーとヒロシマ(24)~(26)」、広島県医師会速報第926-928号、昭和53年(1978年);同著『平和の勇者ドクター・ジュノー』、蒼生書房、1989年、pp.214-230)。(9)オリジナル資料では、この一文はジュノー博士が肉筆で書き足している。(10)鈴木九万(すずきただかつ1895-1987)公使のことである。同公使は1936年8月に外務省を退官していたが、1942年12月から外務省条約局の中に設置された「外務省在敵国居留民関係事務室」で嘱託として室長を務めていた(「1587鈴木九万」(秦郁彦編『日本近現代人物履歴事典』、東京大学出版会、2002年刊、pp.283-284。内海愛子「日本軍と俘虜―その関係文書と管理機構について」(『東京裁判資料―俘虜情報局関係文書』、現代史料出版、1999年3月、pp.3-43に所収、特にpp.19-20、p.41註(16)。同「加害と被害―民間人の抑留をめぐって」(歴史学研究会編『講座世界史戦争と民衆(第2次世界大戦)』、東京大学出版会、1996年、pp.187-226に所収、特にp.193-195、p.221註(11))。なお、被爆後の広島の現地視察を終えたビルフィンガー氏が緊急救援を要請するために1945年8月30日付で尾道から在東京外務省経由でジュノー博士宛に打電した英文電報の冒頭に「D GAIMUSHO TOKIO 6SUZUKI FOR JUNOD STOP(STOPは電報で終止符を示す。以下略)」(宛外務省東京6(課?)鈴木公使ジュノー博士に以下伝言乞う)とあり、鈴木九万公使に宛てられている。(11)日本国内そして日本軍政圏内では当時、代表がいなかったため、赤十字国際委員会は応急措置として、在日年数の長いスイス人医師パラヴィチーニ博士を首席代表とし、マックス・ペスタロッチ、ハインリッヒ・アングストを現地採用の要員に任じている。在任中に死亡したパラヴィチーニ博士の代替要員として任命赴任してきたのがジュノー博士である。ストレーラー女史は、ジュノー博士にジュネーブから同行してきている。上海在住のビジネスマンであったフリッツ・ビルフィンガー氏も現地採用となった代表である(Cf., Andre DURAND,≪Histoire du ComiteInternatioanlde la Croix-Rouge ? De Sarajevo a Hiroshima≫, Institut Henry-Dunant, Geneve, 1978, pp.463-464.枡居孝著前掲書、pp.29―30)。(12)ビルフィンガー夫人が所持していた日本円の両替のことを示しているのか。(13)「ビルフィンガー・インタークロス」のうち「インタークロス」とは、当時のラジオスイスを介して赤十字国際委員会代表がジュネーブの本部宛に送信した電報(radiogramm)末尾に付された文言である。コールサインのようなものであろうか。「インタークロス」が赤十字国際委員会を意味すると解すれば、「ビルフィンガー・インタークロス」とは、「ビルフィンガー/赤十字国際委員会」ということになり、公私混同の現われということになる。(14)原文では≪mais pour le moment je ne vois pas de caractere criminel ou frisant l’escroquerie≫(しかしながら、当座のところ、人道研究ジャーナルVol. 2, 2013155