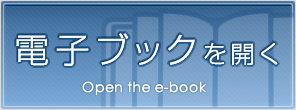「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 51/276
このページは 「人道研究ジャーナル」Vol.2 の電子ブックに掲載されている51ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
「人道研究ジャーナル」Vol.2
The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013さに“防ぎ得た死”であるが、災害関連死に占める高齢者の割合が阪神・淡路大震災では60歳以上が約6割、東日本大震災では95%と多く、19%は病院の機能停止、53%は避難のため移動中ないしは避難生活を原因として亡くなっていたことから(10)、病院や避難途上での付き添い医療ニーズもあると言えよう。2応急対応需要量の推定次に、1の被害量に対し、どれくらいの救護班や病院の対応が必要かについて推定する必要がある。被災地外部からの支援では、派遣準備時間と駆けつけ時間がかかることから、DMAT型医療チームは急性期に間に合わない可能性が高い。一方で、被災現地入りは遅れても、信頼性と確実性、長期間に渡る派遣という被災現地のニーズに合致するのは従来型救護班である。1の患者等の推定に基づき、被災中心地の超急性期から急性期におけるDMAT型医療チームの必要数と、従来型救護班の必要数を想定しておく必要があろう。なお、災害出動経験に長けた救護班は、東日本大震災ではDMATと従来型救護班が保持する医療資機材は異なることに配慮し、両方の装備を携行して被災地に向かっていた。また、過去の被災地は、日常から医療サービスが十分とは言えず、地域医療が崩壊している地域もあり、高齢者の割合が高い地区で、要援護者にも配慮した内科及び外科の広範囲に及ぶ医療が必要となった。災害時の亜急性期の医療活動の充実を図るため、災害医療が長期化した場合の医療対応の検討、こころのケア要員派遣のタイミング等を再検討する必要があろう。時間経過に応じた災害時医療、長期化した時の病院と支部の役割分担の検討が必要である。なお、東日本大震災は、事前に想定し対応を計画していた宮城県沖地震とは規模も被災エリアも異なるものであったが、自らが被災地にいながら、事前計画通りに他地区に支援に向かった救護班もあった。被災者や患者を受け入れて対処すべきか、出動すべきかは、事前計画通りに行かない場合もある。また、津波災害時の患者が来院しない急性期に、船舶やヘリを使うなどで、救護班を医療ニーズの高い避難所や救護所等に派遣するのかを迫られることもあるなど、目の前にある危機に適切に対処するための被害情報の読み解きと状況判断が重要になると言えよう。(2)緊急物資必要量の推定日赤支部や本社では、迅速に物資を届けるための緊急物資必要量の推定方法について、調査研究を行う必要があると考えられる。例えば、緊急物資の当初の必要数は、避難者数(率)を推定し、避難者数から必要量を推定することが求められる。避難者数は、阪神・淡路大震災で最大約32万人、東日本大震災においては、一週間後で約39万人と多いうえ、被害が広域に及んだため、避難所数も多かった。さらに福島原発事故のため、避難先は全国に及んだ。各地方自治体から、「最低3日分の自助努力による備蓄」が住民・企業等に求められているが、避難者数や災害現象により毛布が必要な人数の推定、季節や地域の事情を検討要因に加えるなどで、緊急期の必要数を推定することが求められる。4-2災害事例によって異なる救助基準と公平性の担保東日本大震災では、平常時医療費も無料扱いとなり、広域避難者もその対象となったが、通常の災害時には、被災者の持病薬は無料の対象とならないなど、災害救助基準が災害によって異なっている。災害関連死のリスクの高い高齢者等を含む要援護者が、救援の対象に多数含まれてきている現状から見ると、どこまでを救護班が対応すべきかについても検討しておく必要があろう。また、業務内容についても、東日本大震災では、石巻圏合同医療チームでは、避難所のアセスメント、衛生管理、避難困難者の受け入れ及び安否情報の提供など、本来業務外と言える業務まで実施していた。当時、実施すべき担当者がおらず、人が本来あるべき姿を求めて“人道的”災害救護を遂行するためには、付随する業務が生じたものと解釈すべきであろう。災害救護の実施期間についても、日赤としての明確な“撤退基準”はない。阪神・淡路大震災の頃などは、困った人を助けるために疾風のように現れて救援活動を展開し、地元の自立を見届けると疾風のように去っていく“月光仮面”型の無償の行為が理想とされていた。しかし、社会状況は変容し、災害時の活動についても地域のニーズに応じ、長期化・継続実施される傾向が生じてきている。人道研究ジャーナルVol. 2, 201349