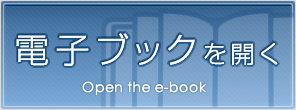「人道研究ジャーナル」Vol.2 page 63/276
このページは 「人道研究ジャーナル」Vol.2 の電子ブックに掲載されている63ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。
概要:
「人道研究ジャーナル」Vol.2
The Journal of Humanitarian Studies Vol. 2, 2013設置した仮分院に移り、復員可能な患者を送り出す一方、空いた病室に原爆症患者を収容した。『きのこ雲』の中の元班員たちの手記にも原爆症の発生が記録されている。「被爆による火傷には蛆が蠢き、医療器具も乏しいので割箸二本をピンセット代わりにしてつまみ出すが、なかなか取り切れない。容体の悪化した患者は、鼻出血、血尿、血便、高熱を出す。紫斑が全身の皮膚に出ている。歯齦出血の口内は拭っても拭っても際限がない。患者は嗽する気力もない。死熱といわれる四二度に体温計が上昇し、何の手当ても受けられないまま患者は死亡する。病室には一度嗅いだら忘れられない悪臭が充満する。何に支えられるでもなく、どうにもならない焦燥と絶望感、そして沈黙。[明日は我が身では?]という不安に耐えながら私たちは懸命に看護を続けた。」(「山峡の静かな村で」)ここでも死者の火葬は看護婦の役割であった。川原での病衣の洗濯、ガーゼの再生、食料品の調達など休む暇もない日が続いた。そして原爆症に対する不安も大きかった。傷もない人が突然に高熱、紫斑、出血や白血球の減少などにより、手当ての甲斐もなく死亡する例を多数見ていたのである。「患者の看護に当たりながら、私たちも白血球測定をしては、あと二、三カ月の生命かも知れないと不安な気持ちを高めた。」(「廃墟から出て」)と元婦長が記している。実際に同班の元婦長であった雪永まさゑは「被爆後は白血球が三〇〇〇以下に減少したまま」であり、「体重も四〇キロを割り、医師の手を離れられず、薬と縁を切ることも出来ない状態が続いた」と同書の中で述べている。しかし戦後は看護教育の場で活躍し、看護歴史研究をライフワークとして『看護人名事典』などの著述を残す功績をあげ、1973(昭和48)年にフローレンス・ナイチンゲール記章を受章する名誉に輝いた。『きのこ雲』の中に「原爆症との戦い」という文章を残した人は、被爆5年後に1年間「原爆症で入院加療した」と記し、そののち結婚したが、「原爆症で国立大阪病院に入院」、女児を3人出産したあとも「私立の原爆指定病院」に入院するなど、「私の半生は原爆症との闘いであった」と述べている。『きのこ雲』のあとがきに、「原爆の後遺症に悩みながら、世の偏見を逃れるために被爆者であることを隠し、ひっそりと罪を犯した者のように生きている人たちがいた。私の班員たちの中にも、そんな人たちがいた」とあるように、心身ともに傷を受けながら、戦後を生きなければならなかった人たちがいたことを忘れてはならない。Ⅳ被爆者救護活動を支えた博愛精神1945年8月6日、この日は広島市内にいたすべての人々にとって生涯忘れられない一日であった。朝方に出ていた警戒警報が解除になり、各自の日課が始まったばかりの時に、突如襲った閃光と爆風は、一瞬にして広島市内を廃墟と化し、死者と重傷者の群れを生んだ。この人類最初の大災厄の中で、自身の負傷をもかえりみず、直ちに救護活動を開始した看護婦たちがいた。『広島の被爆建造物―被爆45周年調査報告書』(1990年刊)(20)の中の「広島赤十字病院」の項の筆者は、赤十字病院の医療従事者たちが、被爆後に直ちに救護活動を行った要因を分析している。「ぜひ注目しておきたいことは、先の谷口婦長の例に典型的にみられるごとく、幸いにも大きな傷を受けなかった者たちは皆一様に、最初の大きな衝撃のすぐ後に、救助活動についていることである。」その理由として筆者は外郭の残った病院にいたこと、その爆弾の特殊性がただちに認識されていなかったこと、またこれまで広島は大きな爆撃をうけていないので、いつかくる非常事態に対する心構えをもち、訓練もされていたであろうことをあげている。人道研究ジャーナルVol. 2, 201361